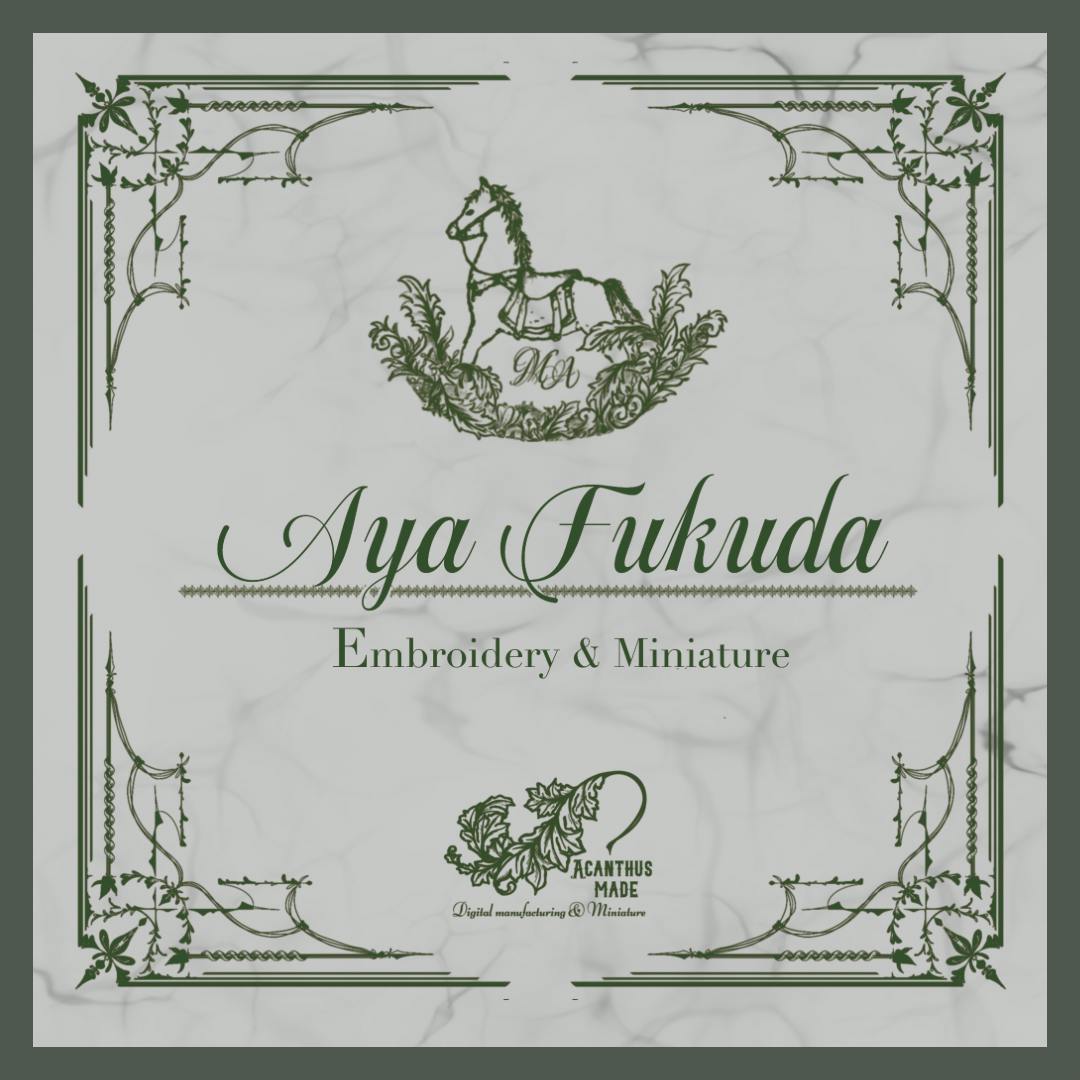刺繍(ハンドメイド)の展示会を開催するには
私は先日、2つの刺繍の展示会へ行ってきました。
2つの生徒展
アリワーク刺繍「ビーズを編む」生徒展
刺繍アートフェスティバルの運営でお世話になっている おおにしみよ先生が主宰する、ビーズ刺繍とアリワーク刺繍のお教室「ビーズを編む」の生徒展。
刺繍アートフェスティバルの出品された生徒さんの作品も展示するということで行ってきました!
作品はフェスの時と少し仕立てを変えて飾られているものもあり、また違った作品のよう。仕立て直しで2倍楽しめる。展示会に合わせて飾る方法を変える面白さを学ばせてもらいました。
そこで生徒さんとのお話で、次からは先生ではなく、生徒主催で開催するとのこと。生徒さんが前向きに動いてくれるとのことで先生は大変喜んでいたのが印象的でした。

白糸刺繍 Aterier Plumesアトリエプリュム
西須先生の生徒さんのグループです。思わず息を呑むほど繊細な、レベルの高い白糸刺繍作品が並び、お話を聞くととても勉強になることばかり。美しい刺繍の裏にはきちんとした想いが込められているんだなと感じました。
その5人の中のうちお二人は元生徒さん。コロナの前に、かなり遠方からいらしてくれていたお二人で、私に動画レッスンのきっかけをくれた恩人でもあります。また以前の私の展示会にも作品を出してくれたことがあるのです。
素敵な白糸刺繍だけでなく、刺繍+ステンドグラスの組み合わせで作品制作もしているユニット「hirondelle」
久々に会えて元気な姿を見れて嬉しかっただけでなく、おしゃべりも最高に楽しかったです

お教室展となるとどうしても中心となるのは先生の作品ですが、このような生徒展では先生一人に注目がいくのではなく、生徒さんみんなの作品を同じ視点で見られるとてもいい機会だと感じました。
私の主宰する「刺繍ルーム」でも展示会やりたい生徒さんいないかな?なんてことを考えながら帰りました。
展示するのは刺繍でなくてもいい。自分の得意なことならなんでもいい。
誰かに自分の頑張ってきたものを見てもらえる機会というのは、素晴らしい体験であり、心を豊かにすること間違いなし!!
ちょっと気になる
なんて人は下の記事を読んで 想像してみてね
刺繍(ハンドメイド)の展示会をするには
初めての展示会 6つのステップ
「いつか、自分の刺繍を飾ってみたい」「個展を開いてみたい」
そんな夢を持つ方は多いのではないでしょうか。
でも、展示会ってどうやって始めればいいの?
ギャラリーの借り方は?どんな準備が必要?
今回は、はじめてでもできる刺繍展示会の開き方を6つのステップで紹介します。
1. 目的を決める
展示会といっても目的は人それぞれ。
たとえば——
教室や仲間の発表会として自分の作品を販売したい
世界観を伝えてブランドを広めたい
他の作家とコラボ展示をしたい
目的がはっきりすると、会場の選び方や展示の雰囲気、作品数まで自然と決まっていきます。
「誰に、どんな気持ちを届けたいか」——ここを一番大切にしましょう。
2、会場選び
刺繍は、糸の艶や立体感を見てもらいたいアート。そのための空間はとても大切です。
会場は下のようなところで探すのが一般的
・レンタルギャラリー(駅近・白壁が多く写真映え◎)
・公共施設(費用を抑えて地元開催も可能)
会場を見学するときは「照明の色」「壁の高さ」「吊り下げ方法」をチェック。
作品の“糸の影”が美しく映える空間を選びましょう。
そして作品やキットなどを販売する場合は、「販売可」かどうか確認を
刺繍展では、作品そのものや図案・キットを販売したい方も多いと思います。
しかし、ギャラリーによって販売可否やルールは異なります。
確認しておきたいポイントは以下の通りです。
・作品・グッズの販売が可能か・販売手数料(委託料)がかかるか(例:売上の20%など)
・決済方法(現金のみ/クレジットOKなど)
・在廊時以外の販売対応(スタッフ販売してくれるか)
・飲食店併設の場合は物販の許可エリアに制限があることも
とくに「販売目的」の展示をする場合は、契約前に必ずメールや書面で確認しておくのが安心です。
3、作品構成
作品が何点くらい飾れるのか。壁面やテーブル数の確認を。
壁面に飾る場合はピクチャーレール、画鋲などの確認。
テーブルはレンタル可能か、持ち込みか。
そして、展示会では“数より世界観”が大事。
5〜10点でもテーマを決めて並べれば、印象に残る展示になります。
たとえば:
白糸刺繍だけを集めて「光を縫う展」花をテーマに「季節の刺繍」
図案の変化を見せる「同じ図案の色違い展示」
額装だけでなく、布に張ったり、立体的に飾る工夫をしてみましょう。
糸の立体感を生かすライティングや、作品にあったディスプレイ小物もイメージしましょう。
4、告知、広報
展示会の魅力を伝えるのは、準備の中で一番ワクワクする部分です。
・Instagram・note・ブログで制作過程を発信・DMやポストカードを配布
・「刺繍展」「embroidery exhibition」などのハッシュタグで投稿
場合によってはポスターや図録などの作成も。
完成までの過程を共有すると、見に来た人が作品により親しみを感じてくれます。
グループ展の場合は参加者全員で発信を。誰か一人に頼ることなく、全員で発信することで一体感が生まれ絆も強くなり、展示会での雰囲気も良くなるでしょう。
「作品を見てもらうには」ということを考え、効果的に宣伝をしていきましょう。
早めに、日時、場所はご案内を。
インスタグラムで発信する毎に必ず掲載し、お客様自身がイベントに来やすい環境作りをしましょう。
5、展示会当日の工夫
展示会当日は、作品を見てもらうだけでなく、
「どんな想いで刺したのか」「どんな時間を過ごしていたのか」を感じてもらうチャンスです。
ほんの少しの工夫で、来場者の心に残る展示になります。
展示会では、作品を通してたくさんの方が声をかけてくださいます。「この糸の色、素敵ですね」と言ってもらえたら、ぜひ笑顔でお話ししてみてください。
ほんの一言の会話から、思いがけないご縁が生まれることもあります。緊張せずに、積極的に話しかけましょう。
販売する場合は、釣り銭・領収書・包装材・在庫管理なども忘れずに準備を。
展示会は出会いの場でもあります。
受付や展示台には、名刺・SNS・HPのQRコード付きカードを設置しましょう。
最近は、名刺代わりに「Instagram QR」や「LINE公式アカウント」のリンクを置く方も多く、“気軽にフォローできる導線”を用意しておくのがポイントです。
そして、1番大切なこと。来場してくれたことへの感謝を忘れずに。
6、展示会のその後へ
展示会での出会いを「次」へ繋げる行動を。
展示会が終わると、ほっと一息。
でも、実はここからが本当のスタートです。
展示を通して得た出会いや感想、写真、経験は、次の活動を育てる大切な種になります。
写真をまとめてブログなどに残す
展示会の様子を文章と写真でまとめることで、来られなかった方にも世界観を届けることができます。
撮影のコツは、作品だけでなく「空間全体」「お客様が見ている様子」「制作風景」も残すこと。
文章では、展示のテーマ・こだわり・当日感じたことを素直に書くと共感されやすく、次回展示の告知やレッスン案内にも自然につなげられます。
ご縁は、宝物になる
展示会に来てくださった方、協力してくれた仲間、会場のオーナーさん。
そのひとつひとつの出会いが、あなたの活動の財産になります。
展示を通して感じた「誰かに見てもらえる嬉しさ」「感想をもらう喜び」は、これからの創作のエネルギーそのもの。
刺繍は、糸で人とつながるアートです。展示が終わっても、そのつながりは静かに、長く、あなたの中で続いていきます。
個展でも、グループ展、販売イベントなど。
何かやってみたいなと思った時が
やるべき時!!
行動力は全部あなたの経験になる。
一度の人生、出会いを大切にし、楽しい経験をたくさん積んでいきましょう!!