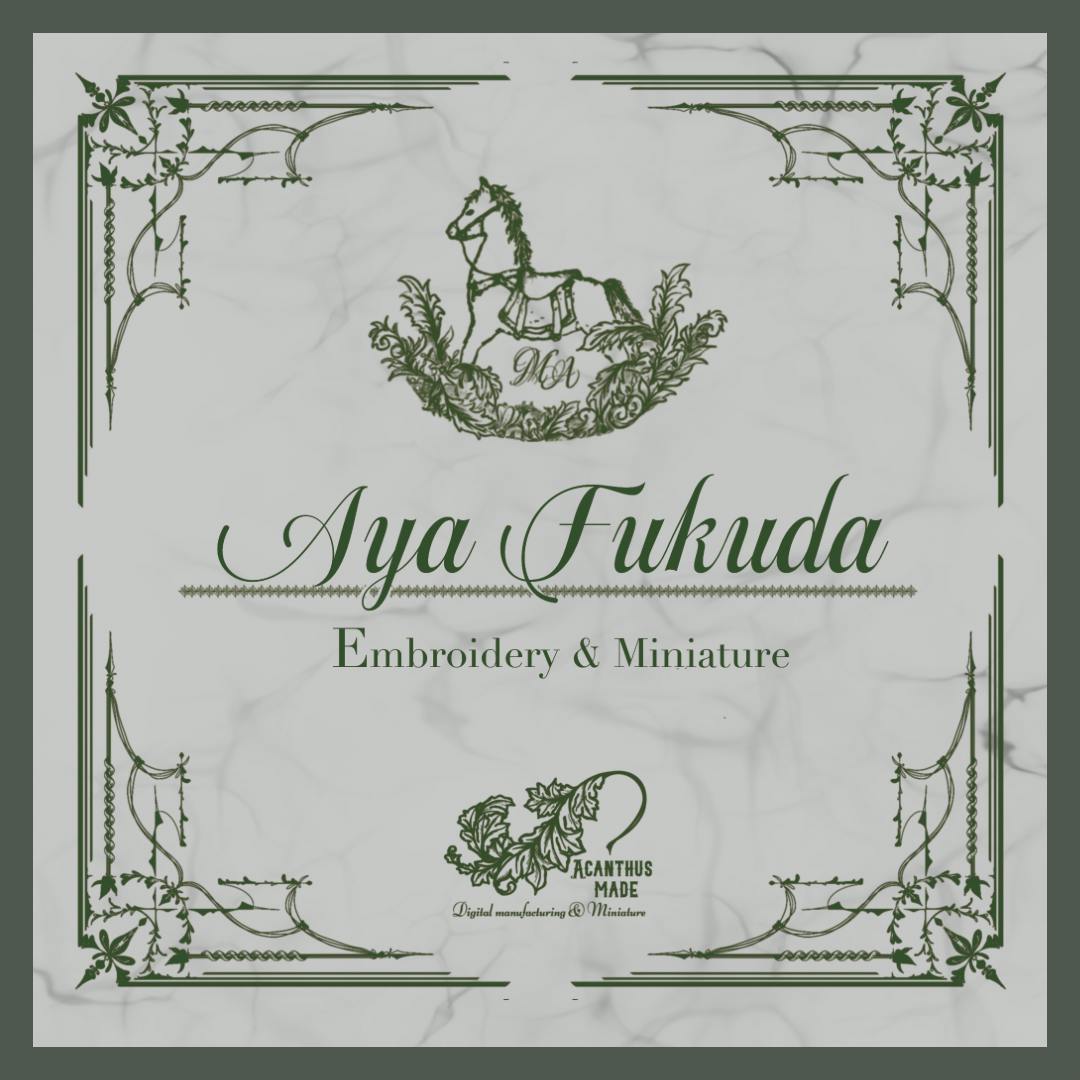針供養
2025/02/08
2月8日 針供養の日
日本の伝統行事 裁縫に携わる人の祈りの日
2月8日が針供養の日と知ってから、毎年欠かす事のできない行事です。
柔らかなこんにゃくやお豆腐に針を刺して、酷使した針を休ませて、針に感謝の気持ちを込めて供養を行います。
一年の感謝と祈りを捧げ、新たな気持ちでまた針仕事を楽しめる。私にとっては一年のリセット、スタートの日と思い、毎年この日を迎えます。折れたり曲がったり錆びたり…集めておいた使い古した針を一つ一つこんにゃくに刺しながら、刺繍を楽しめていることへの感謝と刺繍技術向上を願う時間は心が穏やかになるひととき。
全て刺し終えると、よし!また頑張ろうという気持ちが強くなるから不思議です。
刺繍針、キルト針、
まち針、縫い針、ミシン針
針と一言で言っても様々な種類の針があります。
刺繍でもフランス刺繍針、クロスステッチ針、バリオン針、リボン刺繍針など。さらにキルト針やいわゆる普通の縫い針、ミシン針、ぬいぐるみ用や布団用。まち針や虫ピンも。
使えなくなっていたんだ針を缶に集めておきます。刺繍のレッスン中に生徒さんの使えなくなった針を一緒に預かっておくこともあります。
さらに2月8日には全てのピンクッションの針をぬき、全取り換えして気持ちもすっきりと入れ替えます。
刺繍でもフランス刺繍針、クロスステッチ針、バリオン針、リボン刺繍針など。さらにキルト針やいわゆる普通の縫い針、ミシン針、ぬいぐるみ用や布団用。まち針や虫ピンも。
使えなくなっていたんだ針を缶に集めておきます。刺繍のレッスン中に生徒さんの使えなくなった針を一緒に預かっておくこともあります。
さらに2月8日には全てのピンクッションの針をぬき、全取り換えして気持ちもすっきりと入れ替えます。
針は消耗品
針は永遠に使えるものではありません。気がつかないうちに先端が折れていたり、針自体が曲がっていることも多いのです。「針磨き」という針の滑りをよくする便利な道具もありますが、私は針は消耗品と捉えており、割とすぐに交換します。
目の詰まった布や硬い布に刺繍をした後は必ず交換します。意外と針は痛んでいるものです。
それに気が付かずにしようしている生徒さんも多いので、気がついた時に針交換をお勧めしています。
・糸通しがうまく行かない時、サテンステッチの糸が毛羽立ちやすい時は刺繍針が曲がっているかも。
・狙ったところに刺しにくい、糸が割れやすい。そんな時は刺繍針の先端が痛んでいるかも。
今日はうまく刺せないぞ。そんな日は針交換!
目の詰まった布や硬い布に刺繍をした後は必ず交換します。意外と針は痛んでいるものです。
それに気が付かずにしようしている生徒さんも多いので、気がついた時に針交換をお勧めしています。
・糸通しがうまく行かない時、サテンステッチの糸が毛羽立ちやすい時は刺繍針が曲がっているかも。
・狙ったところに刺しにくい、糸が割れやすい。そんな時は刺繍針の先端が痛んでいるかも。
今日はうまく刺せないぞ。そんな日は針交換!
針はどう捨てる?
さあ、針を交換すると刺繍が上手にさせることに気が付きましたが、この使い古した針はどうしよう。
調べてみると瓶などに溜めておき、危なくないようにして不燃ごみに出す。ガムテープで針をまとめたり、瓶の中にマグネットを入れて置くという記事を多く見かけました。
また、土に埋める。という記事も。鉄なので長い年月はかかりますが土に帰るようです。
そんな記事の中に度々出てきた「針供養」の言葉。針の処分方法を調べたことが私が「針供養」を知ったきっかけでした。
調べてみると瓶などに溜めておき、危なくないようにして不燃ごみに出す。ガムテープで針をまとめたり、瓶の中にマグネットを入れて置くという記事を多く見かけました。
また、土に埋める。という記事も。鉄なので長い年月はかかりますが土に帰るようです。
そんな記事の中に度々出てきた「針供養」の言葉。針の処分方法を調べたことが私が「針供養」を知ったきっかけでした。
針供養、お針様、事始め
針供養は様々な呼ばれ方があり、関東は2月8日ですが、関西方面では12月8日に行われることもあるようです。
事を納める「事納め」事を始める「事始め」両方の意味を持ち、神様をお迎え、お見送りするために慎みを持って、この日は針仕事全般をお休みして過ごしましょう。
針供養の起源は定かではないようですが、なんと平安時代には貴族の間で行われていたと考えられており、江戸時代に入るとその風習は裁縫上達を願うまつりとして伝わっていきます。針仕事は女性にとって重要な仕事だったため、女性のための年中行事でもあったようです。
事を納める「事納め」事を始める「事始め」両方の意味を持ち、神様をお迎え、お見送りするために慎みを持って、この日は針仕事全般をお休みして過ごしましょう。
針供養の起源は定かではないようですが、なんと平安時代には貴族の間で行われていたと考えられており、江戸時代に入るとその風習は裁縫上達を願うまつりとして伝わっていきます。針仕事は女性にとって重要な仕事だったため、女性のための年中行事でもあったようです。
針供養を行う神社、寺は?
全国各地に針供養を行う神社はございます。
関東では浅草寺・淡島堂が有名ですが、元々は和歌山の淡島神社が発祥の地とされています。
皆様のお家の近くでも針供養が行われているか調べてみてくださいね。
関東では浅草寺・淡島堂が有名ですが、元々は和歌山の淡島神社が発祥の地とされています。
皆様のお家の近くでも針供養が行われているか調べてみてくださいね。

川越 蓮馨寺
私は地元、川越の蓮馨寺でお参りをしています。「小江戸」と呼ばれ、古い建物が残存している川越では着物文化もまだまだ多く残っており、この日は特に着物姿のご婦人がまち針がたくさん詰まった瓶を持ってくる姿を見かけます。たくさんのまち針は和裁に使われたのかな?
その着物姿と針供養の様子を物珍しそうに見ている外国人観光客や、一年に一度の針供養行事をとらえようとするカメラマンたち、そしてはたまた寺の境内ではフリマが行われていたり、多種多様の面白い現場が繰り広げられる蓮馨寺はとても不思議な空間です。
朝から15時くらいまでこんにゃくは社務所前に置かれているので誰でも供養はすることはできますが、11時ごろからはご祈祷の参加もできます。その時間に合わせて行ってみるとより針供養を実感できると思います。
その着物姿と針供養の様子を物珍しそうに見ている外国人観光客や、一年に一度の針供養行事をとらえようとするカメラマンたち、そしてはたまた寺の境内ではフリマが行われていたり、多種多様の面白い現場が繰り広げられる蓮馨寺はとても不思議な空間です。
朝から15時くらいまでこんにゃくは社務所前に置かれているので誰でも供養はすることはできますが、11時ごろからはご祈祷の参加もできます。その時間に合わせて行ってみるとより針供養を実感できると思います。